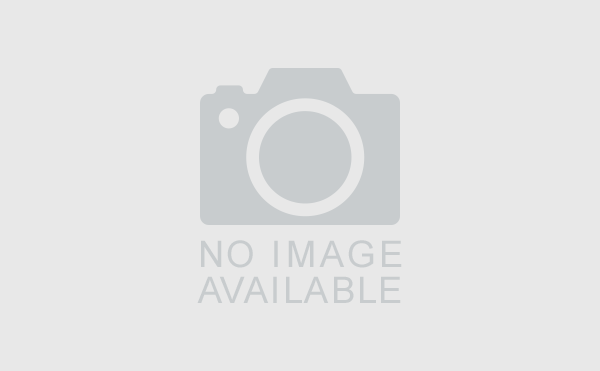指定管理者制度の”新しい潮流”とは ~既指定管理者もこれからの事業者も
指定管理者制度とは?
「指定管理者制度」とは、地方自治体が所有する公共施設の管理・運営を、民間事業者や団体に任せる仕組みです。
いわゆる小泉改革のとき、「民間にできることは民間に」という考えのもと、「民間等のノウハウを活用し、住民サービスの向上に資すること」を目的に、2003年の地方自治法改正により導入されました。
全国の体育館・文化ホール・公園・福祉施設などで広く活用されています。
令和3年4月1日時点での都道府県による導入率は、全国平均で59.5%です。
約6割の施設が指定管理者制度になっています。
入札との決定的な違い
「一般競争入札」は、行政が作成した仕様書に基づいた業務の見積を行い、一番安い価格で落札した業者が業務委託契約で事業を行います。
基本的に裁量権はほとんどなく、仕様書通りに業務をこなすことが求められます。
一方、「指定管理者制度」は、施設などの管理権限を委任する制度です。
裁量権も大きいため、公募時にその内容を提案書で競い合い、審査の上、議会の議決を経て指定管理者が決まります。
そして自治体との協定書という形での契約となります。期間も5年~10年と長いのが特徴です。
制度開始から約20年 ~見えてきた課題と弊害
しかし、制度が始まって約20年。現場では多くの課題が浮き彫りになっています。
1.適正予算の確保の困難化と低価格競争の弊害
自治体の財政悪化に伴う指定管理料の縮減と適正予算の不成立で、応募団体の確保が困難になっています。
また過度なコスト削減志向で労働環境の悪化、「官製ワーキングプア」の発生まで起きています。
2.役割分担とリスク分担の不明確
突発的災害等の危機対応の曖昧さ、施設の老朽化に伴う修繕責任の不明確さなど、役割分担が曖昧であることも課題となっています。
3.民間活用の自由度の低さ、自治体職員の理解不足など
仕様書による発注方式(業務委託)による指定管理者の活動の制限、自主事業の制約、収益の減額などが課題となっています。
また、異動による自治体職員の理解のバラツキで「コスト削減を目的とした制度」と誤解されているケース、地域間の格差などもあります。
以上のようなことから「指定管理=安く請ける仕事」という認識が広まったことで、本来の制度趣旨である”民間の創意工夫による質の向上”が置き去りにされてしまったのです。
公共性と収益性のバランスが崩れ、「利益が出ないから撤退したい」という事業者と、「もっと安くしてほしい」という自治体との間に溝が生まれるケースも増えています。
自治体が求めている”新しい指定管理”とは?
そんな中、全国の自治体では、指定管理者制度の見直しが進んでいます。
いま求められているのは、単なる維持管理ではありません。
「地域の活性化」「利用者満足度の向上」「持続可能な運営」この3つを実現できる事業者です。
具体的には、以下のような提案が高く評価されています。
定量的な成果指標の提示
「利用者数を○%増やす」「地域イベントを年○回開催する」など、数字で語る提案力
地域貢献と収益化の両立
施設を使った自主事業で収益を上げつつ、地域の魅力を高める仕組み
運営の透明性と改善サイクル
PDCAを回し、常に進化し続ける姿勢
このような「運営+地域貢献+収益化」が新しいスタンダードになりつつあるのです。
指定管理見直しは大きなチャンス
なぜいま、見直しが加速しているのでしょうか。
背景には、自治体財政の逼迫、人手不足、そして地域課題の多様化があります。
少子高齢化が進み、施設の役割も変化しています。
単に「場所を提供する」のではなく、地域住民にとっての居場所、交流の拠点、経済活性化の起点として機能することが求められているのです。
これから指定管理者を目指す事業者にとって、大きなチャンスです。
指定管理者になるための提案書のポイント
提案書で最も大切なのは、「なぜ自社が最適なのか」を明確に語ることです。
自治体が抱える課題、例えば、利用者の高齢化、若者離れ、施設の老朽化などに対して、「自社ならではの強み」でどう応えるのか。
ビルメン業者なら設備管理のノウハウ、観光業者なら集客の実績、福祉法人なら地域福祉との連携。
その「強み」を、自治体の課題解決にどう結びつけるかを示すことがポイントです。
提案書は、単なる「できることリスト」ではないのです。
事業計画書であり、その内容は実現可能かつ維持しつづけることのできるものでなければなりません。
5年間でどんな成果を生み出し、どう地域に貢献するのか。
そのビジョンを、熱意と根拠をもって伝えましょう。
民間ならではのコスト削減・効率化の例
民間事業者の強みは、「柔軟な経営判断」と「コスト管理」にあります。
例えば、DX導入による予約システムの効率化、多能工化によるスタッフの柔軟配置、地域ボランティアや地元企業との連携による外注コストの圧縮など、まだまだ多くのアイデアが眠っています。
これらの工夫で、質を落とさずにコストを最適化できるのです。
5年間の指定期間で自主事業をどう盛り上げるか
指定管理の魅力は、何と言っても自主事業の自由度にあります。
地域の特産品とコラボしたイベント、観光客を呼び込む企画、地元の学校や団体と連携したワークショップなどなど。
アイデア次第で、施設は「地域価値を生み出すプラットフォーム」になり得ます。
集客や収益の数字も大切ですが、「地域の誇りを育てる」という理念です。
地域住民が「この施設があってよかった」と感じ、自治体が「この事業者に任せてよかった」と思える関係が、更新継続につながります。
指定管理を本気で目指すなら、すぐに準備を始めましょう
指定管理者制度の転換期である今こそ、準備を始めるべきタイミングです。
指定管理者になるためには、多くの情報が必要です。
その情報をもとにした実現可能なアイデアを抽出し、地域貢献と収益化のバランスを検討しなければなりません。
そのため、スケジュールには余裕が欲しいところです。
既存の指定管理施設の情報は、自治体のホームページに掲載されています。
指定管理者の決定は自治体の議会開催時です。そこから逆算すると、おおよその公募時期が分かります。
自治体のホームページに掲載されてから準備を始めるのでは遅すぎます。
できれば1年程度の準備期間が欲しいものです。
時間的に余裕があれば、そもそもの自社の強みを再検証できます。
そして自治体の課題を見直し、情報開示請求で過去の実績を調べ、現場を何度も確認することで地域住民の声を集められます。
その結果、より良いアイデアや作戦が出てきます。
地域のこれからを考える、実に楽しい時間です。
地域で御社の力を発揮しませんか
指定管理は、単なる「仕事」ではありません。
地域と共に成長し、社会的価値を生み出す経営の舞台です。
その舞台で、あなたの会社の力を発揮してみませんか。
事業アイデアをメインに、指定管理やプロポーザルについてまとめたサイトを公開しています。
こちらも参考にどうぞ。
(ボタンが表示されない場合はこちらへ:指定管理&プロポーザルのアイデア)